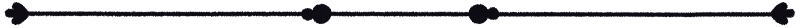やっと過ごしやすい時期がやってきましたね!🍂 今年は、本当に、夏が長かったように思います。 昼夜の温度差がある時期でもありますので、皆さん、体調管理にお気をつけくださいね😊
早速ですが、前月の9月は、認知症月間でした。 西成区では、西成図書館のご協力を頂き、認知症関連の書物やオレンジチームのチラシ、ケアパス(認知症の情報をわかりやすく示したもの)を展示していました。 展示様子は、前記事にあります(^^)
先日、館長様へ来館者の様子を聞きに、行かせていただきました。以下、館長様からのお言葉です。
・昨年から始めましたが、昨年よりも、立ち止まって手に取って見られておられる方、借りて行かれる方が明らかに増えていました。
・オレンジチームのチラシやケアパスの持ち帰りも増加。
・年齢増は、中高年が中心。けれど、絵本を借りられていくお母さまもいた。読み聞かせで借りられたのかもしれませんね。
・福祉関係の方と思われる方も借りて行かれていました。
図書館の協力のもと、ありがたいお言葉を頂きました。
認知症は、誰しもがなる可能性のある病気です。 認知症は、お年を重ねた人だけがなる病気とも限りません。40代、50代、60代でもなる可能性がある病気でもあります。
❝独りで抱え込まないでほしい❞ 支援をしていると、常々、思うことであります。
オレンジチームは、本人様やご家族様からの相談だけではありません。 支援される専門職の方からも「こういう状態なのですが、どうしたらよいですか?」などの 相談が入ることもあります。
悩むのは、本人も家族も支援する専門職も皆、同じです 。 だからこそ、一緒に悩み、一緒に考えていくことを、大切にしたいと思っています 。
地域の集まりなどに出向かせて頂き、認知症の話をする機会もあります。 それでも、早期発見、早期対応が難しい課題を感じています。
館長からお聞きした反響は、興味、関心を持ってもらう取っ掛かりとして、嬉しく思います。
認知症になっても、住み馴れた地域で、安心して生活を送ることが出来る。
その為に、一緒に悩み、一緒に考えられる支援を目指しています。今後も、様々な機関の協力も頂きながら、早期発見、早期対応の課題へ取り組みを続けていきたいと思います。
事前情報💡
大阪市では、9月の認知症月間に認知症の方やご家族、支援者の声を集められ、その“声”を市役所へ展示されていました!
西成区でも、地域の方や認知症カフェ、介護サービス事業所の方々の“声”を集めさせて頂きました。その“声”を西成区バージョンで、展示する機会を検討中です!また、案内させて頂きますね😊